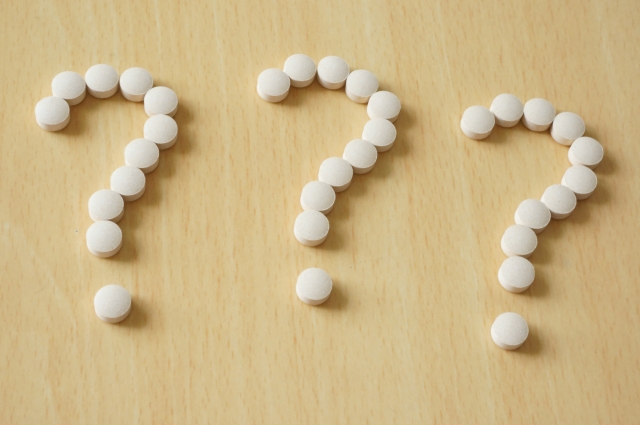退職していざ失業保険をもらうのに、「ハローワークに行く必要がある」くらいは知っている人も多いですよね。
でも、どんな手続きがあるのか、どういう流れになるのかはあまり知られていませんよね。
失業保険を受け取る為には、ハローワークに離職票を提出したり、求職活動の実績から失業の認定を受けたりするなど、さまざまな手続きが必要です。
大まかな流れです。
1、退職後にハローワークで「求職申込み」と「受給資格の確認」を行う
2、「雇用保険説明会」に参加する
3、待機期間
4、給付制限(自己都合退職者のみ)
5、失業の認定
6、失業保険の支払い
この後は「5」、「6」の繰り返しで手当を受け取ります。
この記事では、失業保険が受給されるまでの流れに沿って、失業保険の申請に必要な書類や失業保険をもらうまでの手順を詳しく見ていきましょう。
【1】失業保険の手続きに必要な書類をハローワークへ持っていく
失業保険を受給するには、離職票やマイナンバーカード、雇用保険に加入していたことを証明する書類などが必要です。
この章では失業手当を受けるためにハローワークへ持っていく書類や、ハローワーク初日の流れについて紹介します。
失業保険に必要な書類と失業保険がもらえる期間を知っておこう
失業保険の手続きに必要な書類や持ち物は、次のとおりです。
必要な持ち物
・雇用保険被保険者離職票「1」と「2」
・個人番号確認書類
・身分証明書
・写真
・印鑑
・預金通帳またはキャッユカード
雇用保険被保険者離職票「1」と「2」は、退職して10日前後に会社から送られてきます。
失業保険の手続きに必要な書類の詳細は「記事」で詳しく解説しています。
また、マイナンバーがない場合は、マイナンバーの通知書か、個人番号が記載されている住民票でも大丈夫です。
どちらもない場合は、事前に市区町村の役場で再発行して下さい。
失業保険を受け取れる期間は、原則退職日の翌日から1年間と定められています。
この期間を過ぎてしまうと失業保険を受け取れないので、退職後は速やかに住所地を管轄するハローワークへ行きましょう。
ハローワークで失業保険の手続きを開始しよう!
求職申込書には、学校や職業訓練等の受講歴、希望する仕事や条件などを書き込みます。
求職申込書を記入したら窓口で離職票や身分証明書、通帳などを提出・提示すると、受給資格があるかどうかの認定が行われます。
求職申込書に記入する内容や、内容の詳細は「記事」で詳しく解説していきますよ。
この職員から退職理由や需給資格の有無を確かめるために軽い質問があるので、退職の経緯などの事実を正直に伝えましょう。
本来は「会社都合の退職」なのに、離職票に「自己都合の退職」と記載されていた場合は、ハローワークで正直に事情を話して下さい。
受給資格の認定手続きが終わると、「雇用保険受給資格者のしおり」や「ハローワークカード」をもらってこの日は終了です。
雇用保険受給者のしおりは、次回に行われる「雇用保険受給資格説明会」で必要になります。
ハローワークカードは、今後ハローワークへ行く際に必ず持参して下さい。
【2】失業保険について学ぶ
「雇用保険受給資格説明会」に参加する
ハローワークで需給資格の認定手続きをして1~2週間後、「雇用保険受給資格説明会」に参加します。
ちなみに「雇用保険受給資格説明会」の日時は、ハローワーク初日に伝えられます。
説明会では映像や担当者による講義を通じて、失業保険の正しい受け取り方や、就職活動の進め方などについて学びます。
受給説明会は指定された日の参加が必須ですが、どうしても参加できない事情がある場合は、ハローワークに説明会日時の変更を相談しましょう。
受給説明会の日には「雇用保険受給者資格証」と、「失業認定申告書」が渡されます。
雇用保険受給説明会の日にもらえる書類とその用途
| 書類名 | 用途 |
| 雇用保険受給資格証 | 失業保険の受給資格を証明する書類 |
| 失業認定申告書 | 失業の認定を受けようとする期間中に行った、求職活動を記入する書類 |
これらの書類は今後ハローワークで失業の認定を受ける際に必要なので、なくさないように注意しましょう。
【3】失業保険の受給資格決定から7日間の「待期期間」がある
ハローワークに離職票を提出し、求職申告書を記入した日のことを「受給資格決定日」といいます。
この受給資格決定日から「失業状態にあった日」が通算7日間ないと、失業保険の給付金を受け取ることができません。
【4】失業の認定を受けるために「認定日」は必ずハローワークへいく
7日間の待機期間が終わったら、最初の失業認定を受けるため「初回認定日」にハローワークへ行きましょう。
「初回認定日」の日付けは、求職の申し込みをした日から4週間後の平日と決められています。
自己都合退職の場合は、待期期間後さらに3ヵ月の給付期間があります。
初回認定日はこの期間内に定められているので、絶対に忘れないようにして下さい。
また「初回認定日」以降も原則として4週間に1回、指定された「指定日」にハローワークへ行って、失業の認定を受ける必要があります。
認定日にハローワークへ提出する必要書類は、次のとおりです。
失業の認定に必要な書類
・ハローワーク
・失業認定申告書
・雇用保険受給資格者証
・係員より指定された書類
認定日はハローワークに必要書類を提出して、求職活動の実績が認められるかどうかの確認をしてもらいます。
「失業認定申告書」には、前回の認定日からその認定日前日までの間に行った求職活動の内容を事前に記入しておきましょう。
求職活動の例
・ハローワークが行う職業相談や職業紹介
・求人への応募や面接など
・公的機関が行う企業説明会や職業相談
・就職支援講習・セミナーや職業見学への参加
・再就職のための国家試験や資格試験の受験
もし、「認定日」当日に体調不良があった場合は、ハローワークへ連絡しましょう。
おすすめの転職サイト・エージェントの特徴を比較!特化型サイトも紹介!
【5】自己都合退職の人にはさらに2カ月、3ヵ月の給付制限がある
7日間の待期期間が経過すると、会社都合退職者はその翌日から「失業保険の支給対象者」として認められません。
病気や特定の事情など、いわゆる「正当な理由のない自己都合退職」では、2020年10月1日以降が退職日の場合、給付制限が3ヵ月から2カ月に変わりました。
会社都合も自己都合の場合も、ただ認定日にハローワークに行くだけで失業保険の受給資格は認められません。
ちゃんと就職活動をしていないと、失業保険をもらえないんですね。
【6】4週間に1度、失業認定と失業手当の受給を繰り返す
失業手当が受給されるタイミングは前の証でも説明したとおり、初回認定日から1週間後です。
その後は4週間に1度、指定された認定日にハローワークで失業認定を受けて、28日分の失業保険を受け取る、この繰り返しです。
ただし、待期期間満了日~初回認定日までの支給期間は28日間に満たないので、他期間の支給額よりも少なくなってしまいます。
また、失業手当を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年の間ですが、病気やケガ、出産などで30日間以上連続して働けなくなった場合は、その分だけ延長できます。
いくらもらえる?失業保険の受給額は?
失業保険っていくらくらいもらえるのでしょうか?
大まかに言って、給料の6~8割くらいです。
割合は、賃金の低いひとほど、割合が高くなるように設定されています。
失業保険の手続きや流れをある程度知っておけば、そんなに難しいものではありません。
失業保険の手続きや流れを理解してスムーズに給付金を受け取ろう
失業保険の手続きは、慣れなくて不安だという人も多いですよね。
必要書類や手続きの流れをある程度知っておけば、そんなに難しいものでもありません。
失業手当の受給期間は退職日の翌日から原則1年間なので、退職後はすぐにハローワークに手続きに行きましょう!
また、自己都合退職の場合は2~3ヵ月間の給付制限があるので、すぐに失業保険をもらえるわけではないことも覚えておいて下さい。
失業手当は、仕事を探している人をサポートするためのもの。手当はもらいつつ、より良い転職先を探しましょう。